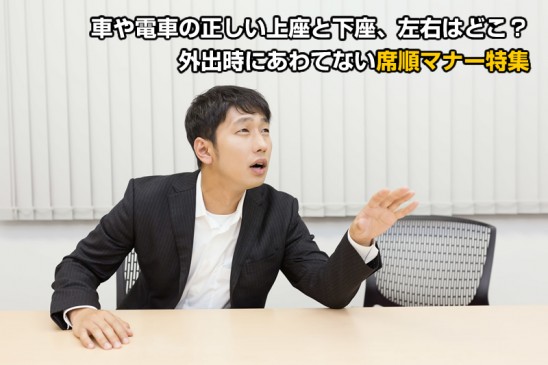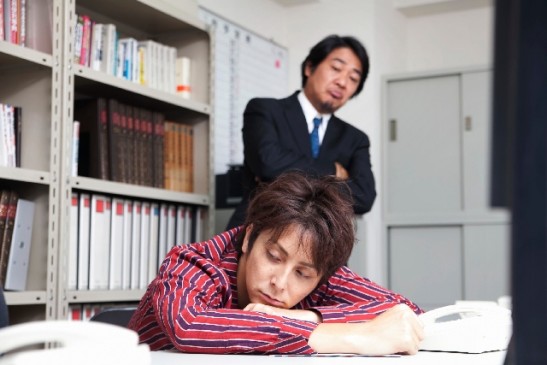数年前から仕事でプロジェクト管理ツールとして”redmine”や”Backlog”を利用していたので、会社でプロジェクト管理ツール”Backlog”を導入したのですが、「みんな!使ってね!」と言っても全く浸透しないので、なぜ使われないのか?というところから、初歩の初歩から解説していく”その2”です。
投稿する時のルールをメンバーに明示しましょう
これはかなり重要です。
最初に課題を作る時の”課題の単位”や”種別・カテゴリ・優先度”や、”課題の取扱い方”、”担当者変更ルール”、”回答ルール”などを決めましょう。
プロジェクトによってメンバーは変わりますのでプロジェクトが立ち上がった最初にメンバーに明示するべきですし、会社としての共通ルールを浸透させることにもなります。
私はよく以下のようなルールを最初に記載します。
一つの課題にはその課題のみ
一つの”課題”の中では、その課題のみについて進行するようにしてください。
急に思いついたときに、別の要件が降ってわいたら、それはそれで別の”課題”にしてください。課題には必ず担当者を付ける
ボールを誰が持っているかを明確にする必要があります。
また、宙ぶらりんになることを防ぎます。担当者は必ず回答
来たボールには必ず回答をしましょう。
自分に来たボールが他の人が担当の場合は、担当者を変更しましょう。担当者を変更する
自分からボールを投げるときは必ず相手「担当者」を変更してください。
課題を作った人が課題を完了する
課題を作った人が最後にステータスを”完了”にして、課題の完了としてください。
以上を運用ルールとして、プロジェクトの最初の”課題”として上げています。
運用ルールなので、普遍的なルールとなります。
この後に、”課題の単位”や”種別・カテゴリ・優先度”をプロジェクトに応じて付与します。
様々な”課題”が乱立するため、その情報を如何にソートしやすくするか、検索しやすくするかが最初に掛かっていますので、プロジェクトを理解しつつ、細かなところまで気が利く人が課題構造を(頭の中で)設計すると良いですね。
例えば、メンバーに周知する課題の件名は「★周知…」にしたり、単発で終わらない課題、例えば複数のフォームの制作があれば「[フォーム]…」とするなどすると、種別やカテゴリのソートのみならず、キーワードでの検索にも有効です。
時に数百となる”課題”といかに付き合うか。
”課題”が10個あっても、軽い物から重い物まで。
しかし目に見える”課題”の数は一緒です。
その数がメンバーに与えるプレッシャーは、内容が重かろうと軽かろうと同じなんです!
良くない例としては、課題と課題の関連性が見えない課題が乱立し、こっちを対応したらこっちにまた新たな課題が発生し、、細かな課題に押しつぶされてしまう。という事があります。これでは元も子もないですね。
なのでそれを最初にある程度設計することで、その仕事、プロジェクトが円滑に進むかどうかにかかっているとも言えます。
今回は以上です。
次回は課題のさまざまな検索方法を記載したいと思います。
ごくごく初歩的な、しかし未利用者向けの内容ですが、まだまだ全然高度で、でも簡単に使える機能がたくさんありますので、また紹介していきますね!