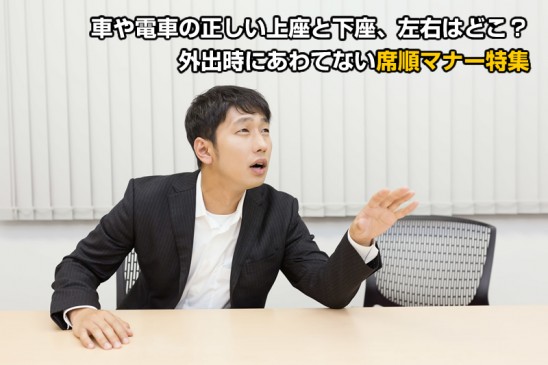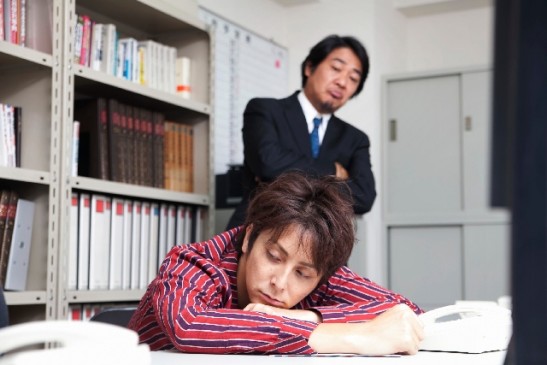これまでの4回では、コミュニケーション(お互いに伝えあい、理解・納得すること)について、言葉(単語)の共通認識・質問すること・伝えること・相手の話を聴くこと、といったことを書いてきました。
「UFOは存在すると思いますか?」~コミュニケーションをとる際に気をつけたいこと。
「正しく問うこと」できていますか?~コミュニケーションをとる際に気をつけたいこと。~その2
相手に伝わる伝え方~コミュニケーションをとる際に気をつけたいこと。~その3
聴き上手になろう~コミュニケーションをとる際に気をつけたいこと。~その4
仕事等でのコミュニケーションは、言葉が中心になりますので、これまでの4回では言葉によるコミュニケーション(言語的コミュニケーション)のことを中心に書いてきましたが、実は言葉以外でのコミュニケーション(非言語的コミュニケーション)も大きなウェイトを占めています。
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションをおおまかに分類すると、下記のように分類されます。
【言語的コミュニケーション】
・話しの内容や言葉の意味
【非言語的コミュニケーション】
・身振り、手振り、態度、表情、視線などの視覚的情報
・口調、声の大きさ、抑揚などの聴覚的情報
少し補足的なことを言うと、筆談や手話については、基本的には言語的コミュニケーションに分類されます。
また、会話の場合は、話しの内容・言葉自体の意味は言語的コミュニケーション、口調や抑揚などは非言語的コミュニケーションに分類されます。
例えば、「最近、調子はどうですか?」「ぼちぼちです」という会話の場合、言葉(言語的コミュニケーションの部分)だけをみると、“可も無く不可も無く”という印象を受けると思います。
では、相手がニコニコ笑いながら、はずんだ声で「ぼちぼちです」と答えていたら、また、逆に沈んだ表情、小さな声の場合はどうでしょう?
この“ニコニコ笑いながら、はずんだ声”や“沈んだ表情、小さな声”といった部分が非言語的コミュニケーションです。
諸説ありますが、言語的コミュニケーションよりも非言語的コミュニケーションのほうが、より多くの割合を占めているとも言われます(コミュニケーションの手段や内容によって、その占める割合も大きく異なると思いますが、言語的コミュニケーションは数%から数十%(半数以下)といった説もあります)。
割合がどのくらいかはさておき、メールのやりとりではなかなか伝わらないようなことが、実際に会って話しをするとすんなりと伝わった、という経験があるかたは多いと思います。
そこにはこの非言語的コミュニケーションが大きく影響していると言えるでしょう。
“目は口ほどにものを言う”ということわざもあるように、言葉だけでは伝わりにくいことを伝えたり、言葉以上の内容や感情を伝える際には、非言語的コミュニケーションの役割が大きくなります。
コミュニケーション(特に電話や対面で)がいまひとつ上手くいかない、といった場合は、非言語的コミュニケーションの部分に注目して、伝え方を工夫してみたり(例えば、重要な部分だけ声の大きさ・トーンを変える)、相手の表情や視線、口調や声の大きさに注意してみると、上手くいくのではないでしょうか。
(建前と本音を使い分けているつもりで、本音の部分が漏れてしまわないようにもご注意を!)